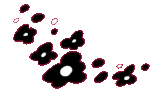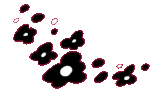∵記憶の扉忘れ去られた扉は再び開かれ、未知なる世界へ彼女を誘う
現実か別世界かどちらか一つしか選べない最大の賭け
本当に大切なものを守れるのは誰か
「……お姉ちゃん、玲良お姉ちゃん!」
「え?」
「どうしたの?お家入れないの?」
「ううん」
夏のまだ暑さの残る日
補習を終えて昼過ぎに高校から帰宅した彼女は家の扉の前で誰かの声を聞いた気がした
きっと暑さに頭がやられたのだろう
今年こそは夏バテをしないように気をつけていたのに、残り少しというところで負けてしまったのだ
「ありがとうね」
彼女は突っ立っていたところに話しかけてくれた双子の幼い兄弟に、しゃがみこんで目線を合わせると微笑んでお礼を述べた
二人の頭を撫でてやると少し擽ったそうにしていたが、彼女が撫で終わると何事もなかったように片手にボールを抱えてもう一方の手を彼女に振ってマンションの下の公園に遊びにかけて行ってしまった
風のように燥いで消えてしまった兄弟が少し名残惜しい
彼らの姿が見えなくなるまで手を振り返して手を下すと、どっと疲れがやってきた
思っていたよりも気を張って夏を乗り切ろうとしていたのかもしれないと、彼女は家の鍵を差して中に入ると玄関で倒れた
「……喉、渇いた」
数時間して喉の渇きで目が覚めた彼女はのそりと体勢を立て直して玄関に座りこんだ
比較的、家の中でも気温の低い玄関に倒れて良かった
部屋だと熱中症になっていたに違いない
鞄の中からペットボトルの水を取り出して一口含んだ
生温い水が喉の奥に流れこんで、本当に冷たい水が欲しくなった
倒れていても誰もいない家がこんなにも寂しいと感じたのは初めてだった
彼女は一人で何もかもしなければならない
「ああ、美味しい」
怠い体に鞭打ってこれではいけないと立ち上がった
台所の水道をひねって冷たい水を飲むと体全体が生き返る気がした
普段なら冷蔵庫の中のミネラルウォーターを飲むのだが、そんな既製のものよりずっと美味しく感じられた
水音が虚しく台所とリビングに響く
「……え?」
選べ、とまた声がした
家の扉の前でした声と同じ低い男の声
誰もいないことを確認して、玄関の扉も閉めているか確認した
幸いなことに、意識がなくなる前に癖で玄関は閉めていた
しかし、空耳は時折近くから聞こえてくる
どうやら暑さで頭がやられたわけではないらしい
一度寝てしまい、水をきちんと飲んだおかげか頭はすっきりと冴えている
それでも、部屋の暑さには耐えられず、声の場所を探しているうちに汗が頬を伝ってきた
「選べ」
声は消えない
消えるどころか、よりはっきりと聞こえてきて気味が悪くなってきた
幽霊か何かが部屋に憑りついているのかとも考えたが、それなら引っ越してきて二年半の今まで何もなかったのは何故だろう
しかも、彼女自身この世のものでないものが見えたことは今まで一度もなく、体質的にも一生ないことを見越していた
「何を選ぶって言うの」
彼女なりに選んで歩んできたつもりだ
高校に合格し、父親が海外に転勤になった際に日本に残ると決断した
両親や兄弟と別れ、早二年半
また、次は大学に向けて彼女はほぼ自分の進路を決めて勉強に励んでいる
家事洗濯と勉強を両立するのは難しいが、どうにかやっている
これ以上、何を選べと迫るのか
生きるか死ぬかなどとふざけたことを幽霊が言ったとしても胸を張って生きると言える自信が彼女にはあので、どうせ出てくるものなら早くこいと構えた
「真実を知りたいか否か」
返ってくるはずもないと思っていた返事はすぐに返ってきて、彼女は拍子抜けした
真実
何が言いたいのか、本当によく分からなかった
彼女にとって真実は現実であるし、別に知ったところで困るようなものでもない
生き死にに関わらないものであると知って、逆にほっと胸を撫で下ろした
「どちらでもいい」
「知りたいか否か」
曖昧な答えは返答にならないらしい
またもや繰り返される言葉に彼女は次第にうっとおしさを感じるようになった
「……知りたい」
口から出た言葉は彼女の意思に反していた
すぐに言い直そうとしたが、今度は自分の声が上手く出ない
どうして、と思っている間に視界が揺れて彼女は突然意識を失った
真っ暗な闇に突き落とされた感覚がした
意識を失ったはずなのに、深層の意識が残っている
「ベアトリーチェ」
あの夢だ
長年、見ることのなかった幼い頃の夢
彼女に決して起こることのない、他人の物語
幼い頃はよく見た夢のはずなのに、随分とあの頃より鮮明にくっきりと見えて手を伸ばせば触れそうだった
しかし、伸ばした手は届くことなく、まるで彼女自身が幽霊であるかのようにすり抜けた
ここはどこだ
真実とは現実とは違うことにようやく気がついたが、もう遅い
彼女は逃げる場所を失って蹲るしかなかった
幸いなことに彼女から真実は見えても真実から彼女は見えないらしい
可笑しな仕組みだと思いながら、ただ身を任せた
宮殿のような場所にベアトリーチェと呼ばれる美しい女が佇んでいた
日本人なら妖精や西洋人形とでも讃えるのではなかろうか
作り物のように磨かれた頬には少し赤みが差していて、緩く波打った金髪碧眼、唇には綺麗に紅がのっていた
長い睫毛に縁どられた強気の眼差しがまだ少女の面持ちを残す
女の横にいる人物も綺麗な可愛らしい少女だった
でも、どこか少女らしくない
何がと言われれば答えられないが、少女と形容するには些か純粋さに欠ける気がした
少女の皮を被った女
ベアトリーチェは少女に言う
「ようやく、腐れ縁のあんたと離れられるわ」
知っている
何度も夢見たから、口に出して続きも言える
「聞いたわ。お嫁に行くそうね。おめでとう」
ベアトリーチェが着ているのは婚礼の白の衣装
「ありがとう。わたしはあんたと違って叶わない夢は見ないの」
そう、彼女も夢を見たのだ
夢を見たのは現実の世界ではない
ここではない場所で、温かい彼女の居場所
ばらばらに散った欠片が、記憶が彼女を駆け抜ける
ベアトリーチェは大した天邪鬼で、本当の気持ちを置き去りにして結婚式は盛大に行われた
相手の顔がはっきりと側で見ていた彼女に見えた
あの顔を彼女は知っている
現実の世界ではない場所で、出会ったことがあるのだ
記憶を探って探って思い出そうとした
物語はその間にも進んでいく
ああ、彼だ
彼女が相手の顔の見覚えを思い出したところで、ベアトリーチェの物語は幕を閉じた
これが真実
気分が悪くなった彼女は再び真っ暗になってしまったその場所で寝転んだ
忘れたつもりはなかった
必死に生きようと、ただの一人の子どもとしてあろうとして捨ててしまったものがあった
「おねいさん、誰だい?」
「……っ」
真っ暗な場所に今度は子どもの声
「お腹が痛いのかい!?」
「お腹より頭が……」
心配そうに跳ねる子どもにどこが本当に痛いのか言おうと思ったが、口に出すことは叶わなかった
大きなものが彼女に迫ってきて彼女の体を覆った
色々なことが一度に沢山彼女に押し寄せてきて、彼女は考えることを放棄した
真実を知ってしまった
知ったところで今更どうにかできることではない
彼女の生きる世界と真実を見せられた世界は根本から違う
彼女の生きる世界が彼女にとっての現実で、彼女には重きを置いている世界だった
大切なものを残してきた世界もあった
そして、真実を知る世界がある
何重にも彼女を取り囲む世界は彼女を引き裂こうとしているようにしか見えない