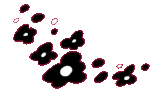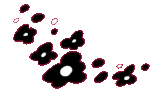∵勿忘草煌の春は青の花が咲き誇る春である
春と言えば、彼女のいた場所では梅や桜が代表的な花なので青が咲き乱れる庭園や城下は物珍しく、近くに顔を寄せて観察していた
「……どこかで見たことがあるような気がする」
どこでと言われれば答えられないが、可愛らしい風貌の青の花はどこぞの野山にでも存在してもおかしくはない
名を知らなくても、知っている
しかし、こうも何処や彼処で見かける花は気になってしまう
「あ、玲良がいたか。兄上はどこにおられる?」
小さな彼女は庭園でしゃがみこんでしまえば、なかなか周りからは見つからない
兄に用事があった白蓮は人の気配を感じてようやく辿り着いた彼女に兄の居場所について訊ねた
「白蓮様。白雄様は書庫におります。探したいものがあるようで」
「珍しいな」
確かに白雄が自ら足を運ぶことは多忙ゆえに少なかった
彼女が彼の小姓になってからは、最初に書庫の場所を教えてくれた以来初めてのことではなかろうか
彼女は花を近くで見るために膝や手にについてしまった土を掃って体制を立ち上がって戻すと、白蓮に微笑んだ
「お待ちになりますか?」
「ああ。お茶を頼めるか」
「はい、すぐに」
庭園の側に置かれた椅子に腰かけた白蓮に一礼して、彼女はお茶の準備に下がる
気候のよい季節だ
外で人を待ちながらお茶を飲むのもまた趣き深い
お湯を沸かしている間に、珍しい香りのお茶を白瑛からもらったのを思い出して、彼女は戸棚から筒を取り出した
彼女のいた場所ではハーブと呼ばれていたそれは貴重なものらしく、白雄のお使いで城下で買い物をしていたときに見かけた値段は相当のものだった
彼女は自分がもらったにも関わらず、勿体なく思って使えずにいた
よい使い道を見つけたものだと自分を褒めて、湧いた湯を使って丁寧に濾した
香ったことがある独特のハーブの香りが彼女を包んで、飲んでもないのに幸せな気分にした
「お待たせいたしました」
お盆で茶器を運んできた彼女は反応のない白蓮が椅子に座ったまま舟を漕いでいたのに気づいて、一呼吸置いてから肩をやんわり叩いた
「お疲れですか?」
「……ああ、すまん。入れてくれるか?」
「でしたら、お役に立てると思います」
このお茶はリラックス効果があると聞いたことがありますから、と言った彼女を不思議そうに見る白蓮に彼女は思い出して疲れを癒す効果があります、と言い直した
「へえ。物知りだなあ」
「お前も少しは玲良を見習ったらどうだ、白蓮」
のんびりした声が響いた後に更に上の方から少し棘のある声がした
白蓮との会話で気づかなかったが、主人である白雄が帰ってきていたのだった
彼女は慌てて頭を垂れる
「!おかえりなさいませ、白雄様」
「ああ、玲良。茶器をもう二つ頼む、一緒に休憩しよう」
「はい」
彼女には怒っていないらしい
相変わらず、白雄は彼女には甘い不思議な方だと思う
普通はこれくらいの地位の人間はただの小姓の人間と同じ卓を同じにして休憩をしたり話をしたりしないものだ
普通でないからこそ、彼女は普通にしていて心地良く過ごさせてもらっている
「何か収穫はありましたか?」
「玲良に聞いたのか」
彼女が声が聞こえないほど遠ざかると、他愛もない話をしていた兄弟は目の色を変えた
「どうせ、書庫になど行ってないでしょう。覗きましたが、いつも通り紅炎しかいませんでしたし。……兄上は何を考えていらっしゃるのです?」
「まだ私の杞憂だ。本当に何か分かれば、お前には伝える」
安易に口にできる問題ではないことは薄々分かっていた
問題はまだ小さく巣食っているだけなのだ
本当の大きな力に踏みつぶされれば、ひとたまりもない
「そうですか。ま、父上や兄上がいる限り滅多なこともありますまい。俺は気楽に構えていますよ」
「……」
四つの青い瞳が春の木漏れ日の中、言い知れぬ不安に揺れた
「お待たせしました」
「ああ、すまない」
「冷めるから、俺は先に飲ませてもらっているよ」
「はい、お構いなく」
彼女はそんなことを知る由もなく、茶器を運び終わって、白雄が飲み始めると自らも椅子を引いてちょこんと側に座った
「風が体の中を通るような、不思議な味がするな」
一口飲んだ白雄が目を一瞬見開いて驚いたように感想を口にすると、白蓮が手を叩く
「流石、兄上。俺もそう言おうと思ってたんです」
「言い得て妙ですね、白雄様」
初めて口にすると不思議な味、匂いがするのだろう
彼女も初めて飲んだときはあまり美味しいとは思わなかったが、しばらく飲むと口に馴染んで癖になる
「どこから手に入れた?」
「白瑛様が下さいました」
「仲良しっていいねえ」
仲が良いということになるのだろうか
白蓮のたとえに彼女は首を傾げた
「白瑛様と私が、ですか?」
「え、嫌?」
「畏れ多いと言いますか、仲良しと言うより良くしてもらっていると言う方がしっくりきます」
身分などあまり関係のない彼女のいた世界なら、近所の姉のような人がかまってくれるとでも言えたのだろうが、ここではそういうわけにはいかない
「やはり玲良を引き合わせて正解だったな。こうして妹弟の知らない面をお前から知れる」
嬉しそうに目を細めた白雄の瞳は彼女から見れば、更に瞳の青が濃くなって見える
濃くなった瞳の色は先ほど物珍しく観察していた花の色によく似ていた
「あ、」
彼女は白雄と白蓮、代わる代わる覗き込むように特徴的な瞳を見つめて、ようやくその名を思い出せた
「勿忘草」
「え?」
「は?」
無言で覗き込まれ続けた兄弟は彼女の一言に拍子抜けして、声を漏らした
「わすれ、なぐさとは何だ」
「花の名前です。あの、庭や城下でもよく見る青い花の」
「……あの花、名前あったんだ」
よく見かけるものだから、この国の皇子であれば当然知っていると思っていた彼女の方が反応に拍子抜けした
「白雄様、白蓮様もご存じなかったのですか?」
二人は顔を見合わせてから困惑したようにそれぞれ呟いた
「いや」
「玲良、ちょっと恥ずかしい話なんだけどさ」
白雄が責めるように白蓮を制したので、彼女はますます気になった
「おい。言うのか、白蓮」
「どうせ、玲良は知るよ」
彼女は調べるのだけは得意である
思い出さなければ、ちょうど書庫で調べようと思っていたところだった
彼女のことをよく知る白雄もそのことを分かっていたので、ここまで知ってしまったら一緒だと観念したのか白蓮を引っ張った手を下げた
「元々は名があったんだろうけど、今では練の花なんて言われて煌でよく好まれて植えられている」
「色が似ているからですね」
瞳の色と言わずとも分かったのか、白雄は頭を掻いた
「実際のところはどう考えられて広がったのかは分からない」
「でも、きっと」
新たな望みに、煌に、練に託した思いが広がって花になったのだろう
煌は建国して間もない国だが、もっと豊かに安定するように祈って植えられた花が国中に広がって、春に各地で咲く
お話だとしても素晴らしいことだと彼女は思う
優しい気持ちで、どのような花も植えられていたのだなと考えていなかったことを考えることができる
「では、花言葉をご存知ですか?」
彼女が首を傾げる両者に微笑んだ
勿忘草には幾つかの花言葉があることを彼女は覚えていた
また、花言葉が一体何のことなのか説明するところから始まったのは別の話である
勿忘草
(わたしを忘れないで、真実の愛・友情・恋)
勇敢提出
ありがとうございました!