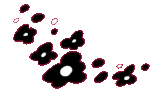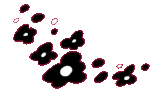∵色褪せた記憶を想うどちらが本当の世界なのか過ごしていると分からなくなる
本当は彼女はここにいるべきなのだと誰かが言ってくれたなら、どれほど楽に暮らせただろう
誰も言ってはくれない
彼女は自分で決めなければならない
「もうすぐお前が来てから一年か。早いものだな、玲良」
彼女は白雄に言われて、もうそれほど経ったのかと実感した
背も少し伸びて、沢山のことを覚えた
「よく働いてくれている、ありがとう」
「そんな、白雄様」
小さく頭を下げた白雄に顔を上げるように、彼女は服の裾を掴んだ
白雄は非常に近い距離の主人だった
無理難題を押しつけることは少なかったが、彼女の能力を的確に推し測って指示を与える
何も分からなかった刺客と思われていた少女は優秀な小姓へとあっという間に仕立て上げられた
彼女の物覚えの早さは白雄の優秀さも物語った
部下を見れば、上司がどのような力量があるのか分かると人は言う
彼女は引き立ててくれた白雄の評判を落とさないように必死で働いた
沢山のことを知って、自らのことも調べた
元の世界に帰りたい
彼女の願いは薄まっていた
異世界に渡る術を彼女は知らなかったし、簡単に叶う願いではないのだと調べれば調べるほど思い知った
それよりもいかに新たな世界で今、生きていくべきなのかを考える時期にきているのではないかと考えるようになった
寂しさは心にあるが、埋めるだけの優しさを彼女は受け取っていた
「いつかは帰るものと覚悟していたが、ますます手離せなくなりそうだ」
「もったいないお言葉です」
「……玲良。もっと私を頼りなさい。お前はまだ十だ。子どもなのを承知して、私は側に置いている」
「はい」
結局、泣き止んだ彼女が今度はつられて泣き出してしまった白龍をどうしていいのか分からなくなり、助けを求めたのは彼女の帰りがまた遅いと心配していた白雄だった
理由こそ聞かなかったが、子ども特有の寂しさから泣き出したのを白雄は悟ったらしい
白龍を宥めた後、彼女が委縮するほど彼女にも優しく接してきた
彼女は必要以上の優しさを拒否してきた
自分が弱くなっていく気がしたからだった
今日は早く寝るように諭された彼女は白雄のお茶を運んでから、先に下がらせてもらった
まだ仕事が残っている白雄を残していくことは心苦しかったが、子どもは早く寝なさいと言われてしまえば従うしかない
彼女のことを探していて今日の仕事が終わらなかったのだと分かっていても、まだ彼女は満足に白雄の手伝いができる年頃ではないのだ
早く早く大人になりたかった
大人になって、白雄や白蓮、白瑛や白龍、それに紅炎といった皇族たちの役に立ちたかった
彼女の願いは変わりつつあった
彼女の部屋に戻るとすぐに温かい寝台に体を滑らせて、明日は早起きして一番のお茶を入れる練習をしようと彼女は心に決めた
今、役に立つことができることを確実にこなしていくのが何れは役に立つことに繋がるだろう
彼女はいつものように瞼を閉じた
「……玲良?」
色褪せた懐かしい母親の声が耳元でして、これは夢だと彼女は首を振った
「玲良!?あなた、今までどこに」
「玲良だって!?おい、どこか痛いところは?怪我はしていないのか?」
父親の声に首を横に振った
大丈夫だよ
守ってくれていた人が側にいたのだと言いたいのに、思うように言えなかった
全てが懐かしくて愛しかった
目を開けると、広がった世界に彼女は絶句した
戻っている
立っていたのは玄関の前
彼女は裸足で髪の毛は長く伸びていた
一年という歳月は長く、彼女のことを元の世界の者たちは諦めかけていたことを会話から知った
彼女はただ泣いた
泣き続けて泣き疲れて眠って、夢の世界ではないのかとまだ信じられないでいた
なくしたものは大きかった
失ってしまえば、恋しくなるのは当然だった
彼女は一人、時間が止まったかのようだった
何を言われて調べられて答えても大人たちは首を捻った
煌だの魔法だの、信じてもらえるわけがないのに彼女は必死に話し続けた
神隠しだと周囲は騒いだ
興味を持っていた周りや家族も冷め切ると、彼女を嘘吐きと呼び始めた
賢い彼女は本当のことを幾ら話しても駄目だとようやく現実を理解して、本当の嘘をつき始めた
一度、嘘を話してしまえば簡単だった
嘘は嘘で塗り固められ嘘の彼女が出来上がった
「……白雄様」
彼女が望んだものはこれほど冷たいものだったのだ
戻りたいと願っても、もう二度と戻ることはできないかもしれない
冷たい本当の彼女の世界で暮らすことは彼女自身は何の不満もなかった
ただ心配していた
さよならも言わずに出てきてしまったこと、きっと優しかった彼らは心配しているに違いなかった
そんな彼女の気持ちも年が経つにしたがって、薄情なもので薄れていった
彼女は大人になった
彼女が元の世界に戻って八回目の夏が過ぎようとしていた
「行かなきゃ」
行かなければいけないという心の奥の使命感は残っていた
でも、どこへ
彼女は彼女自身を見失ってしまった