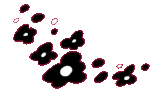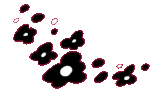∵君の孤独に触れた日人は皆、人には簡単には言えない孤独を抱えて生きている
口にすれば、きっと更に孤独が増すかのように思えるから胸の奥にしまっている
大人になっていくほどに、隠し事は大きくなる
「元気がないな、玲良」
「……わたしが、ですか?」
「どうした、また何かジュダルとあったのか?」
あの出来事は白蓮から無事に白雄に伝わった
物凄く怒られると覚悟していたのに、呼び出された白雄から彼女が受けた仕打ちはただ白雄に静かに抱きしめられることだけだった
その日は頗る白雄は静かで、彼女も従って静かに過ごした
雨がしとしとと降る少し寒くて冷たい日だった
次の日からまた昨日みたいだったらどうしようと悩んでいた彼女だったが、白雄は吹っ切れたようにいつものように明るく少し心配症に戻っていた
彼女は安堵した
「ジュダルとはあの日以来、会っていませんから」
「そうか。風邪でも引いたか?」
彼女の額に手を乗せる白雄だったが、その体温は自らのものと大差ない
あれも違うこれも違うと彼女が元気がないことを前提で進む原因探しに彼女は苦笑した
「わたしは元気ですよ、白雄様」
「ああ、それならいい」
彼女が白雄の心配性に微笑んだので、ようやく白雄は納得したらしい
大人しく執務に戻っていった
白雄の側に控えて、飲み終わった茶器を片しながら彼女は白雄の様子を窺ってまだ気づかれていないと胸を撫で下ろした
相変わらず鋭い人だ
突然のことに焦りさえしなければ、彼女の奥の方まで見抜く目を持っている
彼女は白雄からそっと隠した本の表紙を撫でながら、これからどうするべきか思案した
「何か分かったのか?」
書庫に本を返したときに彼女がある一冊まだ借りっぱなしにしていることが気になって、紅炎は書庫を訪れた彼女に声をかけた
あまり自分から声をかけることがない紅炎からの問いに彼女は面食らった
「本が一冊返ってきていないのは、お前が忘れているからではないだろう」
「……すみません。すぐに返します」
逃げるように帰り、再びやってきた彼女は紅炎の気配が書庫にないことを確認して本を元の場所に戻した
紅炎も馬鹿ではない
問題の一冊の題を確認済みだったので、彼女がこっそり来るだろう時間は予想して席を空けていた
そして、ようやく彼女から返ってきた古ぼけた本を今度は紅炎が手に取った
「ルフと魔法の関係、か」
最近出入りが激しくなっている組織の中でも神官と呼ばれる地位にいる不思議な少年、ジュダルは煌では珍しい魔法使いだ
しかも、魔法使いの中でも特異な存在で頂点に立つマギという存在らしい
彼女は白雄の小姓であるから、主人が毛嫌いしているジュダルとはあまり言葉は交わさないだろうが、紅炎にはよくちょっかいを出してくる
お前のルフは面白い、マゴイの量は常人とは比べ物にならない、時が来たら王にしてやる
あまりにも褒められ、調子の良いことばかり並べられるので紅炎自身もいい気はしながら期待してはいない
今の煌の皇帝は伯父で、ほぼ従兄が次の皇帝になることも決まっている状況で期待する方が無謀だと言えた
「お前に魔法は使えないぜ、紅炎」
そんなことを考えていると、ジュダルが退屈そうに本棚を眺めながら紅炎に近寄ってきた
珍しいこともあるものだと、紅炎は愉快気に口角を上げた
「どうしてだ?」
「魔法は素質みたいなもんだからな。あ、あいつはなかなか見所がある」
「あいつ?」
魔法自体珍しい煌で見つかった魔法の素質のある者に紅炎も興味が湧いた
「玲良。知ってんだろ、よくここに出入りしてる皇子のお気に入り」
「……ああ」
やはり彼女かと心の奥底で期待して分かっていたが、実際にそうなのだと知ると紅炎の気分は一気に沈んだ
「あいつ、人のルフを見てる」
「ほう」
「目の焦点が違う場所にいくことがあるだろう?俺らのルフを観察してんだよ。素質はあるけど、仕えてるのが皇子じゃなあ。今のところ、手が出せない」
きっと、ちょっかいでも出して断られ、牽制されるに至ったのだろう
組織が入りこんで間もない煌ではまだ影響力が乏しい
心底残念だとジュダルは口をへの字に曲げた
欲しいおもちゃが手に入らなかった子どものようだった
「魔法が使えるとさぞ便利だろう」
幾ら敵対していると言っても、ジュダルと彼女が探求しているものは同じだ
協力とまではいかないが、紅炎も最近は彼女の影響からか何かよく分からない魔法というものに興味を持って知ろうとしていた
「まあな。でも、玲良の場合はちょっと違うかもしれねーな」
彼女は魔法がなくても生きていこうとしている
魔法を何故か拒絶している
彼女の周りを取り囲む空気は澄んでいて、白いものに溢れていた
魔法など必要としていなかった
このままで、いつまでもずっと一緒にいたかっただけだった
「でも、そのうち変わる。魔法使いは孤独だから」
「孤独?」
「他人には見えないものが見える、触れる、使える。見えない者には一生分からない苦しみさ」
彼女がいつまで耐えられるかと面白そうに笑ったジュダルはもう子どもの顔をしていなかった
「白龍様は寂しくありませんか?」
「はい?」
「年が離れていらっしゃいますでしょう。白雄様とは滅多にお会いできませんし、家族の繋がりが薄いような気はしませんか?」
資料を手離した彼女はその足で白龍を探して会っていた
鍛錬をしていた白龍の側に座って見守りながら話をした
「他の家族と比べたことがないので、何とも言えませんが。僕には何より近くで姉上がいますから、あまり考えたことはありません」
「白瑛様は白龍様のお母様のようですものね」
優しい姉、側にいなくても心配してくれている兄たち
白龍はよく分かっている
近くにいるから家族なのではない
近くにいなくても離れていてもお互いに思い合っていれば、それが家族なのだと
「……玲良は、寂しいのですか?」
「え?」
「玲良にも、母国に家族がいますよね?」
日本とはどのような場所で、彼女はどのような家族だったのかと白龍は純粋に興味があった
しかし、ある程度仲良くなるまでは相手のことを深く聞くのは失礼だとも分かっていたので聞けずにいたのだ
「寂しいなんて、罰が当たります」
弟である白龍よりも小姓である彼女と白雄は一緒にいることが多い
とてもよくしてもらっている
最初から今までずっと
慣れないことにも、周りからの視線からも家族のように守ってくれる存在に彼女は恵まれた
感謝しなくてはならないとずっと考えてきた
その一方で、やはり九歳の子どもだ
疎外感を感じて寂しい、元の世界に帰りたい、帰る術が知りたいとも思っていた
あまり温かい家族とは言えなかったかもしれない
それでも、彼女にとっては大切な普通の家庭だった
「白雄様には本当によくしてもらって、白龍様とは友達になって」
「でも」
「ごめんなさい」
彼女の堪えていたものが決壊した
白龍は突然、顔を覆ってしまった彼女を心配するしかなかった
自分が泣かせてしまったかもしれない罪悪感に苛まれた
「……ごめんなさい。少ししたら、戻りますから」
彼女さえ笑って堪えていれば、何もかも元通りになる
白龍は鍛錬の手を止めて彼女の横に座り、そっと寄り添った
彼女が元に戻れるように願った
どう声をかけていいのか分からずとも、共にいることは自分にもできる
彼女は白龍の優しさに嗚咽を漏らした