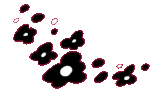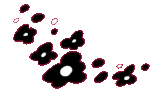∵夜風に消えた赤い絲赤髪
その色を他人は血の色だと蔑んで、地位の低い傍系の皇子を笑った
直系の皇子に仕える彼女もまたそうだろうと諦めていた
「これか」
背後から近づいた大きな影は背伸びをした彼女を追い越して、目的のものを本棚から取り出した
よく書庫に現れる小さな者だ
自身の弟や妹とそう変わらない年齢だろうに、噂によると従兄の白雄の小姓をしているらしい
「ありがとうございます」
彼女は振り返って本を取り出してくれたその人物にお礼を述べた
威圧感のある大きな体に強面の顔、真っ赤な髪
小さい者から見れば恐怖を感じずにはいられない風貌だが、彼女は親切にされたせいか不思議と威圧感は感じなかった
手助けが済むと何も言わずに奥に行ってしまった赤い人に少し興味があったものの、彼女は白雄から用事を言い遣っている
心配させてしまうことの方が怖れられて、後ろ髪引かれつつも白雄の部屋に戻った
「ああ、紅炎だ、それは」
彼女は休憩の間に先ほど書庫で出会った人物の話をすると、白雄は知っているようで頷いた
「こう、えん様?」
聞いたことがあるようなないようなその名に首を傾げる
「私の従弟にあたる者だ。戦場に行かないときは、よく書庫に現れると聞いたことがある」
白雄の従弟
当たり前のことだが、白雄たちにも血の繋がりのある親戚がおり、その多くが仕えている
紅炎もまた然りで、武芸に秀でており戦に駆り出されていることが往々にあるらしい
「いつもいらっしゃるのでしょうか?」
「気になるのか?」
人との関わりを自ら積極的に持つ方ではない彼女が紅炎を気にかけるのは意外だった
「どこか寂しそうだったので気になって」
一人で書庫にいる様は自ら望んでそうしているようにも見えたが、彼女はその姿に引っかかりを覚えた
何が違うのか
温かそうな髪と瞳の色に対して、瞳の奥は冷え切っていて、あまり多くのことを考えないように生きているように思えた
考えても仕方がないと諦めているようにも思えた
「寂しそう、だったか」
「あ、紅炎様がおっしゃったわけではありませんよ」
「分かっている」
あの従弟はそんな弱みを人に簡単に見せる人間ではない
自分の家族のことで精一杯で、父方の弟の従弟の長子である紅炎のことまで手をかけている暇がないというのが正直な感想だった
忙しくしているうちに距離は開き、いつの間にか従弟としてよりも一人の部下として把握し指示し共にいる
彼女には目をかけて小姓にまでしてしまったが、意外に身近な人間ほどに近すぎて大切にできないものかもしれないと彼女に言われて白雄も少し寂しく思った
そして、彼女はまたいつものように書庫に通い詰める
借りてしまうときもあるが、その場で読み進めて時間が経つときもある
用事だったり自ら調べていることだったりする
紅炎はいつもいるというわけではないが、比較的いることが多いようだった
いるときは奥の方で気配がするので分かる
「紅炎様」
彼女から声をかけたのは初めてだった
「何だ」
ゆっくりと視線を本から彼女へと上げた紅炎は彼女が自身の名を知っていることを少し意外に思った
主人である白雄にでも聞いたのだろうか
「……その、上にある本が取りたいので、申し訳ないのですが、ずれていただけないでしょうか?」
紅炎が座るゆったりとした椅子の背にも本は並んでいた
彼女が探しているものはその場所にあるらしい
背表紙を探し、すぐに見つけて手にすると、重ねて置いていた本の山にまたその探し出した本を乗せた
「ありがとうございます」
彼女は紅炎を振り返って礼を述べた
紅炎は気にする風でもなく、一瞥して座ると本の中の文字の羅列に視線を落とした
「あの、紅炎様」
彼女は立ち去らずにその場に残っていた
「何だ」
「本が好きなのですか?」
「それを聞いて何になる」
第一皇子の小姓と言えども、たかが小姓が皇族に随分と普通の、変なことを聞く
「わたしも好きなので。と言いますか、探しているものがありまして」
「歴史、言語くらいしか俺は網羅しておらん」
紅炎の言葉に彼女の目が輝いた
「白い鳥、黒い鳥、ルフ、日本、どれか一つでも何か書いてあるものを知っていましたら、教えていただきたいのです」
「何の呪文だ、それは」
彼女は普通の小姓ではないことは噂で紅炎の耳にも届いていた
白龍、白瑛を狙った刺客だった者を物好きにも白雄が自らの下に置いた
すぐに首切られるだろうと思われた小姓はよく働いて気に入られているらしい
しかし、やはり奇妙な者には変わりなく、小姓のくせに頭が高いともっぱらの評判だった
「……すみません。帰ります。読書のお邪魔をして申し訳ありませんでした」
「待て」
実際に目の前にいる彼女を見ると、頭が高いのとは少し違う気がすると紅炎は感じていた
彼女はよく書庫に訪れる勉強家で、ひょっとしたら知性がある小姓よりももっと優れた者なのかもしれないと思うようになっていた
下手に恭しくされるよりも、ある程度の礼を尽くされてもはっきりされる方がかえって心地よい
思案していた紅炎が黙ったままだったので、気を悪くしたと勘違いした彼女は去ろうと山になった本を抱えようとしたので、紅炎は引き止めた
「日本については、これが良いだろう。ルフというのはお前の言う白い鳥、黒い鳥の総称だ。ルフについてはこの本棚だ」
「これ、全部ですか?」
紅炎の横に並ぶ本棚には百は下らない数の本が並んでいた
彼女は驚いて、興味深そうに幾つか手に取る
「ああ、細かいのを入れるともっとあるが」
「ありがとうございます!」
大量の資料を見つけて、またしばらく通い詰めることになりそうだと彼女が本の棚を見つめていると、そんな彼女の背後に紅炎は立った
「お前、名は?」
「申し遅れました。水瀬玲良です」
「どんな字を書く」
「えっとですね」
持っていた紙と筆を懐から取り出すと、水瀬玲良と力強く書き記して紅炎に渡した
「よい字だ」
「ありがとうございます」
紅炎を怖く思う者もきっといるのだろう
しかし、彼女は紅炎の知識に感心していたし、本当のところの疑問や質問をしっかりと投げかけてくれることを有り難く思っていた
「お前はしっかりしているな。何歳になる?」
こうも意思がはっきりしている子どもに会うのは珍しい
気になって年を訊ねたが、やはり予想していたよりも若いことに紅炎は驚いた
「九つ。もうすぐ十でございます」
「紅覇や紅玉と同じくらいか。……しっかり勉めよ」
「はい」
幼い子どもの頭に手をやると、幼い弟妹のことが頭を過った
しばらく会っていないが元気にやっているのだろうか
これほどまでにしっかりしなくてもよいが、皇族末席を担う者としてしっかりと彼らの成長も長子である紅炎が見守っていかなければならない
「あの、紅炎様」
「まだ用事か?」
わしゃわしゃとしばらくは紅炎の思うがままに頭を乱された彼女は恐る恐る口にした
「わたし、白雄様が素晴らしいのは周りの方々がきっと素晴らしいからだと思っていました。やはり、紅炎様のような方が支えていらっしゃるのですね」
「……」
純粋なのか牽制なのか分からない口をきく彼女の言葉を紅炎はしばらく黙って聞いていた
「これからも皇子を支えてください。心よりお願いします」
「分かったような、口を」
皇族の苦しみは皇族にしか分からない
しかし、彼女の苦しみもまた紅炎には分からない
いつ切り捨てられてもおかしくない彼女の立場で、主人である白雄を信頼し従っていくと覚悟を決めているのがどこかおかしかった
「紅炎様の髪の赤、わたし好きです。温かくて火のようで扱いを間違えれば怖いけど、きっと怖いばかりじゃない」
紅炎の不器用さは夢の中の人の不器用さに似ていた
ああ、そうかと彼女は話しながら何故紅炎がこれほどまでに気になるのか分かった
「だから、紅炎様の名もとても良い名だとわたしも思うのです」
紅炎には自分の心を切り捨てて生きる後悔をして欲しくない
願わくは繰り返すことがないように