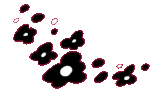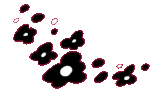∵悪戯な君の指先刺客(見かけ上)から小姓として引き立てられた彼女は正しく金魚の糞だった
彼女を引き立てた人物、第一皇子である練白雄はその様子を微笑ましく感じていた
彼女はよく気が利くし、物覚えも早い
小姓としては十分の働きをしてくれているのにも関わらず、それ以上のことをしようとして失敗して成功して一喜一憂している様は普段、あまり手をかけてやれない末弟と重ねてしまい、ついつい余計に可愛がってしまう
「玲良」
「はい、お茶ですね」
「玲良」
「はい、書物庫に返して参ります」
「玲良」
「はい、白蓮様ですね。ただいま呼んで参ります」
名前の呼び方の調子で白雄が何が欲しいのかが分かるらしい彼女は熟練の従者のようで、実に優秀だった
可愛がっていると言うよりも重宝して白雄自身も無意識に離したくないというのが本音だった
「休憩しないか、玲良」
「はい」
彼女は人一倍気が遣えるのに、上からの提案には遠慮せずに素直に応じる
上の立場の者から声をかけられると畏れ多く、床に膝をつき、顔を上げるように言われるまで頑なに上げなかったり通り過ぎるまで黙っていたりする者が多い中で、臆せずにいる彼女は本当はどこかの国の姫ではなかったのだろうかとさえ思わせられる
初めて会ったときに遠い地、日本では彼女は学生だと聞いた
話を聞ける機会は少ないし、彼女自身も自分のことをあまり話したがらないので無理には聞きだしていないが、相当質の良い教育を受けているのだろう
「……これは見事だな」
「女官の方が、白雄様にと。工芸茶と言うらしいですよ」
休憩だと言ったすぐに運ばれてきた茶器の中には花が段々と開いて浮かぶ
彼女は不思議なものだと興味深そうに様子を窺っていたが、白雄も同様だったらしい
注がれたときの香りや味も見事だった
「慣れたか」
「はい。皆さん、よくしてくれます」
茶器を傾けながら彼女は微笑む
刺客と思われていたと思えないほどに、待遇は良い
兵士からは第一印象が悪かったからか未だに警戒されている節があるが、彼女の働きは少しは認めてくれているらしい
重たい荷物などを運んでいる際に手伝ってくれる者も出てきつつある
「困ったことは何かないか」
「困ったこと、ですか」
あるにはあるが言い出していいものか迷っていることはあった
元の世界のことだ
彼女なりに調べていると、日本という国はあるそうだ
ただし、ここでは倭と呼ばれているらしい
どうして白雄の口からも日本と出たのか分からないが、どうやら勝手に変換されている言葉が幾らかある
それはまだいい
日本は鎖国中だと書物庫で出会った人物から聞いた
日本から自分は来たのだと言うと、意外そうに目を見開かれた
人の出入りも厳しく制限されている日本から人が来るなど聞いたことがないらしい
彼女の知っている日本はこの世界にはないのだという事実
伝えてどうにかなるわけでもないが、ここまで引き立ててくれた白雄には話しておくべきなのだろうと判断して彼女は顔を上げた
「どうした?」
「わたしは日本から来ました」
「ああ」
彼女の所作から忘れた日は一度もない
白雄は何れは手を離さなければならないだろうということも心のどこかで覚悟している
「でも、その日本はわたしの知っている日本ではないのです。わたしが生まれ育った日本ではなさそうなのです」
おかしい話だと思っていた
初めて会った彼女は日本と口にした
嘘をつくにももっともっともらしい嘘をつくべきではないかと頭の片隅で思ったが、必死に生きようとする姿勢には好感を持った
そして、彼女は無事に白雄の小姓になり少しずつ探っていた
「調べていたのか」
「はい」
「玲良、私も調べて考えていたのだが……お前の日本はこの世界にないのではないだろうか」
彼女の考えていたことと全く同じことを白雄に言い当てられて彼女は面食らった
「例えば、別の世界があって何らかの歪みで此方に飛ばされたと考えれば、納得がいく」
「どうして、歪みなんか」
「それは私にも分からないな。まだ調べる価値はありそうだ」
「そうですね」
胸につっかえていたものを吐き出した彼女が再び口にした温かいお茶は心にまで沁みるようだった
「玲良」
聞きなれない声色で名前を呼ばれて、彼女ははっとして白雄の顔を下から覗き込んだ
粗相でもしただろうか
先ほどまでのんびりとした時間が流れていたはずなのに、少し変わった呼び方をされて空気が硬くなった
「白龍と白瑛とはまだ会う気にはならないか」
「……すみません。気を遣わせてしまって」
「いや、あんな出会い方なら仕方ない。私も忙しくてなかなか付き添ってあの二人に会うことができなかった。今度、時間ができそうだから一緒にどうだ?」
「白雄様と一緒に、ですか?」
家族団欒を邪魔しやしないか
久しぶりの兄に会える時間を、第一印象最悪の人物と過ごす時間へと変えてしまう不安があった
彼女が困惑しているのを責める様子もなく、白雄は軽く彼女の手を握った
どんなに優秀な部下だとしても末弟の白龍と同い年くらいの幼い子どもの彼女を安心させ、いざとなれば守ってやれる自信はあった
初めてが最悪なら、後は上がるだけだ
白雄の小姓として一緒にいて過ごしてくれるのは助かるが、それではいつまで経っても同世代の友人ができないのではないかと内心は心配していた
「皇族という立場上、あの子たちには友人が少ない。もし、玲良がいいと言うなら紹介して友達になってやって欲しい」
「お友達に、わたしが?」
「ああ」
「なれるでしょうか」
生活が変わってから同世代よりも少し上の年齢の者たちと付き合うことが多くなった
どうやって友達を作っていたかなんて忘れてしまっている気がする
「なれるさ」
「……はい!」
白雄は彼女にほんの少し勇気をくれる
躊躇っていたことも前へと踏み出すことができるように背中を押してくれる
ついこの間、敵のように出会ったはずなのに救ってくれたのも居場所を作ってくれたのも、これからの人との繋がりも彼だった
「まあ、もしなれなくても大丈夫だ」
「え?」
「……本当は、私はできるだけ離したくないんだ」
「お側にいますよ?」
「そうだったな」
彼女が嬉しそうに屈託なく笑うものだから、白雄も何も分かっていない彼女に苦笑を漏らした